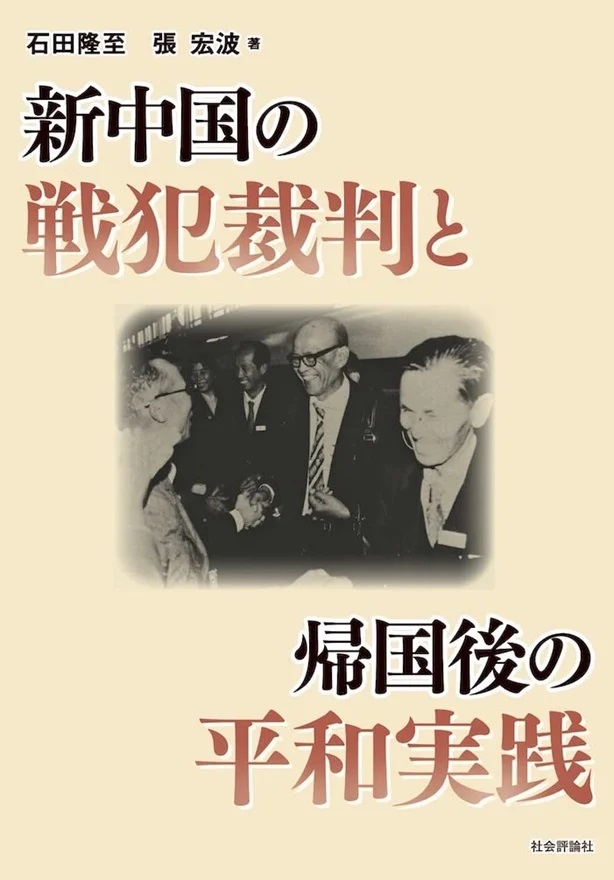「新中国の戦犯裁判と帰国後の平和実践」
・・・・ここまでの議論を踏まえれば、中国が東京裁判の結果に対して不十分さを感じていたことが見て取れる。事実、中国代表判事であった梅汝璈(メイルーアォ1904-1973)は、侵略戦争の土台となった西欧列強や日本の帝国主義の次元にまで判決が迫りきれず、更なる戦争の発動を抑止しきれなかったことを限界の一つとして指摘している。・・・・・
その梅は、新中国による戦犯裁判の準備にも大きく関わっていた。・・・1948年11月に東京裁判が終結した後も、梅汝璈はしばらく東京に滞在していた。国民政府からは政務委員兼司法部長(法務大臣に当たる)として任命されたが、拒否していた。1949年10月に新中国が成立すると同年12月に北京に到着した。外交部(外務省に当たる)の顧問に就任し、国際交渉の経験と国際法の専門知識を提供することになった。・・・
法的根拠の成立過程を論じる上で、もう一人欠かせない専門家が王桂五(ワンゲイゥー 1918-1995)である。・・・1954年に最高人民検察署が日本人戦犯処理業務団を組織した後、それを担当する検察官300名あまりの事前研修を、当時最高人民検察署副秘書長だった王が担当することになった。戦争犯罪に関する専門的知識が不足していると感じた王が依頼したのが梅汝璈である。・・・王桂五らは、ニュルンベルク裁判や東京裁判、国民政府裁判の法的根拠や判決まで詳細に検討していた。東京裁判の限界点を明確にし、新中国裁判でそれを克服しようとする問題意識を持っていた点が興味深い。本来処罰すべき犯罪が大国の政治的干渉によって妨げられた欠陥として、特に次の三点が指摘されている。
①天皇の不起訴により国民的な戦争責任意識の形成が妨げられたこと、
②財閥の不起訴が戦後の軍国主義復活の経済基盤になったこと、
③植民地支配の責任を問わず、朝鮮半島、台湾・中国東北などでの隷従化の罪が放置されたことである。・・・(本書75P~78Pより抜粋)
誕生したばかりの新中国は日本軍国主義の戦争犯罪とどう向き合ったのか?
個々の戦犯の戦争犯罪を裁くだけではなく、帝国主義の植民地支配そのものを裁くとはどういうことなのか?そのために中国の人たちはどういう実践を行ったのか?今までにない新しい視点から「新中国の戦犯裁判と帰国した戦犯たちの平和実践」を紹介しています。